形名
(model number)
メーカが商品を特定するための番号(文字列)。呼び方はメーカによって型名、型番、品番、型式など様々なので、「モデル番号」というのが無難かもしれない。PCで「かためい」を漢字変換すると型名になるので、「型名」の方が一般的と思われがちだが両者の頻度はほぼ拮抗している。たとえば代表的な計測器メーカの横河電機や安藤電気は「形名」。型を使うのは「型番」「型式」も多い。形名の命名方法は各メーカ独自だが、大体2通り。
1つは番号の羅列で、使う番号が無くなると桁数を増やすやり方。HP(現キーサイト・テクノロジー)が代表で、たとえばデジタルマルチメータの34461Aやネットワークアナライザの8753Dなど。形名の末尾には必ず「A」を付け、改良(大きな性能変更を伴うバージョンアップ)があるとB、C・・と形名を更新するのが同社のやり方(一部例外はある)。同社の旧モデルは機種群によって形名に法則性があり番号を見ただけで機種群や基本仕様がだいだい想像できたが、(番号の枯渇からか)近年は頭にアルファベット1文字を付けている。RF
製品はEやN、安価な基本測定器はUやBだが、その命名法則は不透明で形名から機種群を推測できなくなった(筆者は、同社の年配の営業マンに確認したことがあるが、社員でも法則はわからないらしい)。
2つめはアルファベット(英文字)2文字(か3文字)と数字4文字(4文字以外も時々ある)のケース(アルファベットと数字の間に「-」やブランクがある場合もある)。アルファベットは大文字の事が多く、アンリツのMS2690Aシグナルアナライザ、日置電機のIR4051絶縁抵抗計、リオンのUV-15振動計など。国産メーカは前述のキーサイト・テクノロジーのように数字だけの形名が多かったが、(数字だけだと何かわかりにくいので)頭2文字に機種群が想像しやすいようなアルファベット2文字を付ける形名に変更する傾向がある。たとえば日置電機のIRはInsulation Resistance(絶縁抵抗)の略、エヌエフ回路設計ブロックのWF1974ファンクションジェネレータ(FG)は同社のFGの通称(ニックネーム)であるWaveFactory(ウエーブファクトリー)を略したWFを頭に付けている。
形名のつけ方はメーカの自由だが例外として各メーカ共通の法則が、日本の電源と最近のオシロスコープ(オシロ)にある。たとえばテクトロニクスのオシロスコープMSO3054の05は500MHz、4は4chを表し、ほとんど世界中のオシロの形名の末尾3桁は周波数帯域と入力チャネルを示す。菊水電子工業のPMC18-3は18V/3A仕様で、数字が電圧/電流レンジを表すのは他の国内電源メーカもほぼ同様。キーサイト・テクノロジーの電源形名がこの法則に従えば日本での売上は増える、という笑い話がある。
アンリツの形名の頭は計測事業部門の製品はM、旧電話機事業部門の製品はE(例:EF111Aコールシミュレータ)。2文字目はカテゴリー(機種群)の略でスペアナはS、信号発生器はジェネレータのGである。パワーメータは2文字目がLだが、光通信製品という区分がないので、形名からは光パワーメータ(たとえばML9001A)とRFパワーメータ(たとえばML2437A )は判別できない。同じ電電ファミリーだった競合の通信計測器メーカである安藤電気(現横河計測)の形名はAXyyyyという書式で、Xは機種群を規定する英文字(大文字)で、yyyyは数字である。光通信製品は「AQ2140光マルチメータ」のように、2文字目がQなので、光であることが形名だけで(品名がなくても)一目瞭然である。

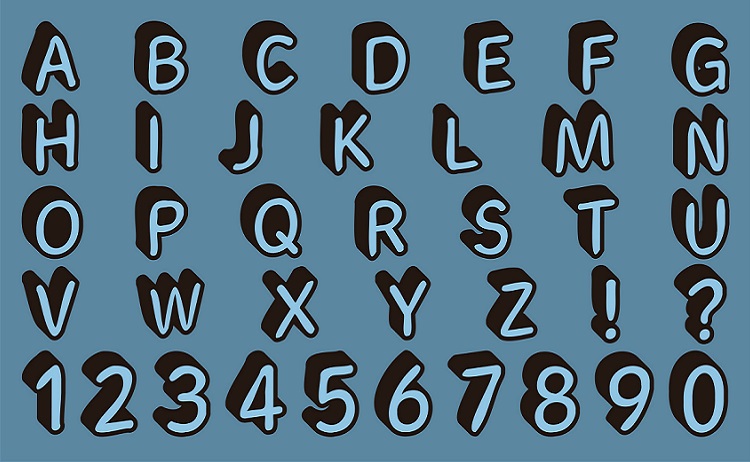



.png)